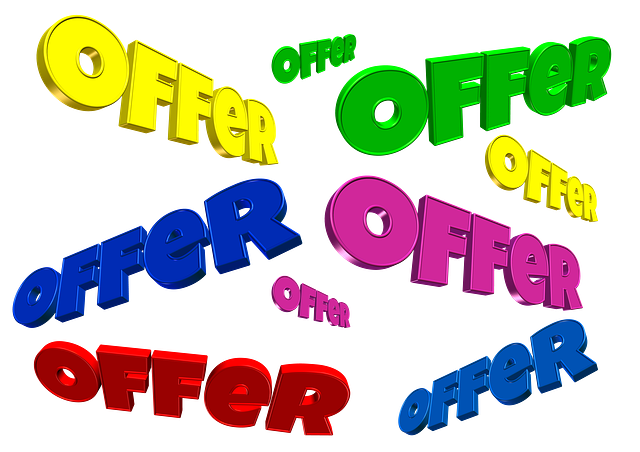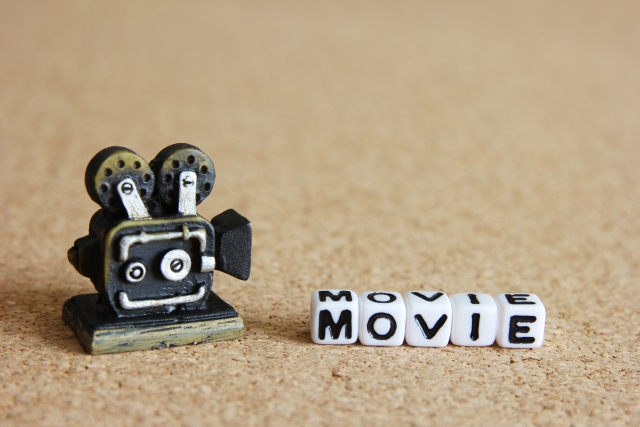『サービス』や『製品』にはライフサイクルがあります。
つまり『製品の寿命』です。
新サービスや新製品を販売する場合だけでなく、既存の商品においても、
自社のポジショニングはどの段階にあるのか?絶えず把握しなければいけません。
把握する方法は2つ!
- 【新サービスや新製品のライフサイクル】を中心に考える方法
- 【ユーザーへの普及率】を中心に考える方法です。
2つの視点を比較しながら、同時進行で考えると戦略が考えやすくなります。
新製品・新サービスのライフサイクル
まずは、製品のライフサイクルを中心に考えてみましょう。
新サービスや新製品は、
- 【導入期】
- 【成長期】
- 【成熟期】
- 【衰退期】
の4段階を経て世の中に浸透していきます。
①導入期
新サービスや新製品を世の中に送り出すタイミングが【導入期】です。
この段階では、売上も利益もありません。
いわゆる投資の段階といえます。
まずは、世の中の人達にしってもらうことが重要ですので、
広告やPR、SNSの拡散などのプロモーションが最も大切な戦略になります。
広告宣伝の失敗がそのまま事業の失敗にも成りかねません。
ネーミング・コピー・競合他社との差別化などの失敗は許されません。
広告代理店の選定も非常に重要な段階だと言えます。
②成長期
世の中にその存在が認識され、売上や利益が急速に伸びていく段階です。
この時期になると、競合他社が参入するだけでなく、新規企業の参入なども目立ってきます。
後から参入してくる企業は真似するだけですので、有利な点も多々あります。
改善や価格戦略も練りやすい点があります。
自社ならではのブランディングによる差別化がされていることが重要です。
導入期の段階で、競合他社の参入も見込んだ戦略が構築されていなければいけません。
③成熟期
ライバル企業との競争が激しくなる段階です。
ある程度のポジショニングが確立されていても、『シェアの奪い合い』『価格競争』などにより、売上や利益が落ちてきます。
場合によっては、他社に抜かれることもあり得ます。
日用品では、スーパーなどでの値引き販売が普通になってくるでしょう。
成分のバージョンアップ、パッケージの変更などが必要になってきます。
④衰退期
市場は飽和状態です。
より良い他社の類似製品により市場が奪われているかもしれません。
また安価な模造品なども多く出回っているかもしれません。
いずれにしても、売上・利益ともに右肩上がりは望めません。
初期投資の費用が回収されていれば、市場からの撤退も選択肢です。
多くの企業が撤退を始める可能性もあります。
成熟期同様に、バージョンアップやパッケージの変更だけでなく、
日常的なセールなどが必要になってきます。
このような状況になると資金力のある大企業が有利になってきます。
バージョンアップやリニューアルを繰り返している洗剤や柔軟剤などは、
成熟期や衰退期の最も分かりやすい例でしょう。
生き残っている製品は、大企業もしくはブランドが確立されている製品です。
ユーザーへの普及率
製品のライフサイクルの裏では、ユーザへの普及率も同時に進行しています。
今度は、次にユーザーへの普及率から考えてみましょう。
【新サービスや新製品が世の中に普及していく】状況をユーザーに対する普及率から考えるのが【イノベーター理論】です。
【イノベーター理論】は
- イノベーター
- アーリー・アダプター
- アーリー・マジョリティ
- レイト・マジョリティ
- ラガード
の5段階に分かれます。
①イノベーター(普及率2.5%)
イノベーターは、いわゆる「オタク」層です。
PCやスマホ、ゲームなどが発売された時に徹夜して購入するような層です。
この層は全体の2.5%という少数派ですが、電気製品などはイノベーター層から普及していくのが普通です。
②アーリー・アダプター(普及率13.5%)
イノベーターのような専門的な知識はありませんが、
『便利そうだな』『良さそうだな』という実用面から検討し購入する層が【アーリー・アダプター】です。
「アタク」ほどではありませんが、「新しもの好き」な層です。
ユーチューバー・インスタグラマーのような、最新の情報を誰よりも早くアップロードしたり、
流行の先取りをしようとする層です。
影響力もあり、企業が、口コミ拡散の為の戦略『口コミマーケティング』に活用するのは、この層だと言えます。
つまり、インフルエンサーであり、インフルエンサーに影響力のある人達です。
③アーリー・マジョリティ(34%)
【イノベーター】や【アーリー・アダプター】の行動を確認してから購入する層です。
この層は、多数派を構成しています。
【アーリー・マジョリティ】まで到達できれば事業は成功と言えるでしょう。
多くの企業は【アーリー・マジョリティ】をターゲットとし戦略を構築しています。
④レイト・マジョリティ(34%)
「みんなが使っているから」という理由で購入する慎重派層です。
この層も多数派を構成しています。
どこにでもいますね「みんな買っているから購入する」「みんな並んでいるから私も並ぶ」的な人。
【アーリー・マジョリティ】が増えれば、自然と行動してしまうので、ターゲットとしては比較的容易だと考えられます。
⑤ラガード(16%)
購入が見込めない層です。
「新しいものに興味が無い」また「新しいものが嫌い」な層です。
このような方は、必ずいます。
新規のアプローチには向いていませんが、
既存の企業としてはリピーターとしては非常に有難い層とも言えます。
まとめ
製品のライフサイクルを考える時には、ユーザーの行動も同時に考えると効率的です。
- 【導入期】【成長期】には、ターゲットである【イノベーター】もしくは【アーリー・アダプター】に対する戦略が必要です。
- 【成長期】から【成熟期】に掛けては【アーリー・マジョリティ】に対する戦略が必要になるでしょう。
- 【成熟期】に向けての【レイト・マジョリティ】の獲得や、【衰退期】での生き残り戦略などが必要になってきます。
戦略の組み合わせは、新製品の内容や競合他社の状況により異なりますが、おおよそ上記の様な考え方が中心になります。
【ラガード】層は少数派ですので、費用対効果の面からも必要は無いでしょう。
もし、あなたが広告代理店に勤務している場合、広告主の製品が『今どの段階にあるのか』『購入しているのはどの層なのか』
改めて考えてみましょう。何か発見があるはずです。