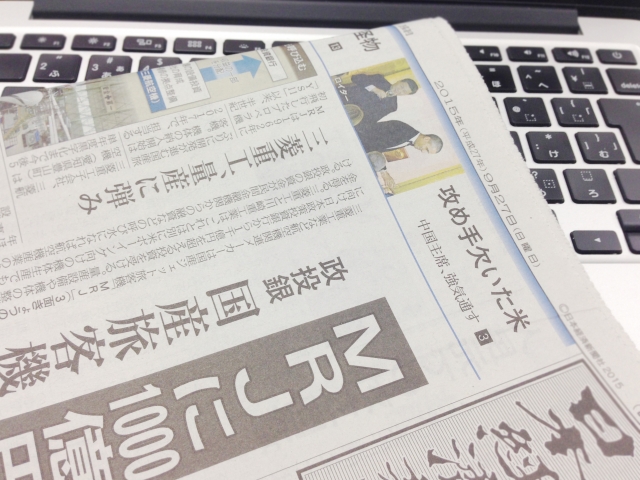広告で大事なことは!
『広告で重要なこと』
今回は大きなテーマです。
全てに通じることを簡単に記述することはできませんが、
広告にとって、大切な事をお伝えさせていただきます。
日常生活の中で、
あなたは『こんな一方的な広告じゃ商品売れないだろ!』と思う機会が多いはずです。
きっと、毎日のように目にしていると思います。
Webサイトが普及し、バナー広告も個人作成できるようになり、安価に広告掲出ができるのようになった結果、
会社の規模に関係なく多くの企業が広告を掲出できるようになりました。
その結果、一方的な広告が多く見受けられるようになりました。
自社の商品特性や価格など『伝えたいこと』を訴求することが安易になった為に、
言いたいことを一方的に訴求してしまうのです。
言いたいことを減らすのは大変です。しかし、全てを伝えてしまうと(自慢話し)のオンパレードになってしまいます。
このような広告が生活者から受け入れられることは多くありません。
広告で忘れてはいけないこと!
広告を掲出する場合に絶対に忘れてはいけないこと。それは!
『生活者は広告を全く信用していない』
ということです。
この前提を忘れてはいけません。
なぜかというと!
生活者がWebサイトなどで広告を見ているということは、
その時点で、『競合他社の情報や口コミ』を検索し、正しい情報を集めている状態だと判断することができます。
多くの情報を集めることが出来る時代において、1つの広告を見て簡単に購入する人は皆無です。
特にサプリメントや化粧品の広告を見ている人は100%その状態です。
- ブルーベリーのサプリメント飲んでいるが全くよく見えるようにならない。
- 1か月で「シミが無くなる」美白の化粧品ですでに3か月目。何も変化がない。
- ダイエットのサプリメントを2か月飲んでいるが1キロも減っていない。
- 即効性のある育毛剤を1瓶使ったが、逆に減ったような気がする
- 体臭予防の石鹸を購入したが、朝の通勤時から実感がない
- ダイエットしたいが、苦労しないで痩せるサプリで何も変化がない
上記の様な口コミを見て情報を集めています。
つまり、特定のWebサイトを見ている人はのほとんどは、その類似商品の利用者の声を調べ、
疑惑の目で広告を見ている状況です。
広告は疑惑の目で見られている
今、利用しているサービスや商品に満足していない生活者は、
広告を最初から疑惑の目で広告を見ています。
- この商品も結局一緒だろ?
- みんな同じようなことばっかり言っているな
- これも大袈裟な広告だな
- まともそうな商品って中々ないな
- 初回500円だけど、どうせ複数回購入で2万円くらいいっちゃうでしょ。
- 良いことしか書いてないけど、口コミと全然違うじゃん。
生活者は広告を見る前の段階から疑っているんです。
特に安価なインターネット広告は顕著です。
生活者は、聞いたことのない小さな企業が、簡単に立派なランディングページを作成して広告をしていることをちゃんと理解しているのです。
広告に必要なのは【信頼性の獲得】
最初から広告を疑っている生活者の心を引き付ける為に、最も必要なことは『信頼性の獲得』です。
『信頼性の獲得』なしに売上を継続させることはできません。
しかし、多くの企業は、商品やサービスの訴求をして、『参ったか!』と価格訴求して終了です。
『こんな良い商品で初回500円なんだから、みんな購入するだろう!』って思い込んでいるんです。
- この商品はこんなに凄いんです。
- なぜなら、こんな根拠や実績があるからです(証拠の提示)
- 今なら初回500円で、30日以内なら返品自由です。
多くの広告は、この流れですが、2が非常に弱いんです。
ひどい場合は一切抜けている場合もあります。
商品に自信があるが為に抜けてしまうんです。
残念ながら、この感覚では商品は全く売れません。
なぜなら、競合他社も全く同じだからです。何1つ差別化が出来ていません。
世の中、1社だけが断トツの商品なんてありません。
多数の企業が同じレベルのサービスを販売しているのです。
信頼性を獲得する方法
信頼性を獲得する方法は、『具体的な数値』と『小さな約束』そして『マイナス面の告知』です。
具体的な数値
具体的な数値は必ず必要です。
具体的な数値を提示して、なぜその数値だと効果があるのか?証明しなければいけません。
証明している機関も重要です。
『利用者の声』は当たり前です。アマゾンで買い物する人でレビューを参考にしない人はいません。
今の時代、生活者は利用者の声も疑惑の目で見ています。
その多くが関係者であることくらい知っているんです。
『利用者の声』を掲載すればOKだ。という感覚はもう通用しない時代です。
小さな約束
多くの商品で効果を実感できていない生活者に対して、大きな約束は意味がありません。
疑惑の目をごまかすことはできません。
- 3日でシミが消えます。
- 1週間でマイナス10キロ達成
- アッという間に10歳若返り
- 1週間で1サイズのバストアップ確実
というような広告だと、本当に困っている人から一定数の反応があるかもしれません。
しかし、このような広告だとリピーターはいませんので、
広告を掲出し新規顧客を獲得し続けなければいけません。
どこかのタイミングで事業はストップします。
上記のような約束よりも、確実な小さな約束の方が生活者の心に響きます。
- 使用を続けることで、少しづつシミが薄くなることが証明されています。
まずは3か月しっかりと続けてください。 - 1か月で1キロ減量を目指す方法です。時間は掛かりますが、身体に負担を掛けない為に
リバウンドしずらい身体に近づけます。ダイエットは時間を掛けることが重要なのです。 - 気になる箇所にしっかりと栄養を届けます。吸収率は〇%を達成しています。
〇%以上で初めて肌の奥まで届くことが証明されています。 - バストアップには『マカ』が良いことが証明されています。
なぜなら、〇〇だからです。しかしながら、バストアップには個人差があることは否定できません。
一方で『マカ』には〇〇な効果がありますので、幅広く女性の方に満足していただけるのが
『マカ』の特徴です。
上記のように、大きな約束よりも、小さな約束の方が効果があるのは確実です。
大袈裟な広告が氾濫している中で、逆に目立つかもしれません。
マイナス面の告知
あえて、マイナス面を白状するのも良い手です。
どうせ口コミでマイナス面は知られています。
その内容を自ら記載して、マイナス面をプラスに変える方法や、メリットに対して小さなデメリットであること。
などを消費者に伝えるのです。
そのことで信頼性がアップする可能性は非常に高いと言えます。
また、信頼を得ることは、リピーターにつながる可能性も出てくるのです。
『この企業は信用出来そうだな』となれば、その後のチャンスも大きく広がります。
もし、今実施している広告に効果がないのであれば、『信頼性の獲得』が足りないのかもしれません。
生活者は、企業が思っているより全然賢いのです。
あなたの広告は『自社の自慢話しに終始していませんか?』そのような一方的な広告は生活者には通用しない。
もし通じたとしても、リピーターにはなりません。
ということを肝に銘じておきましょう。