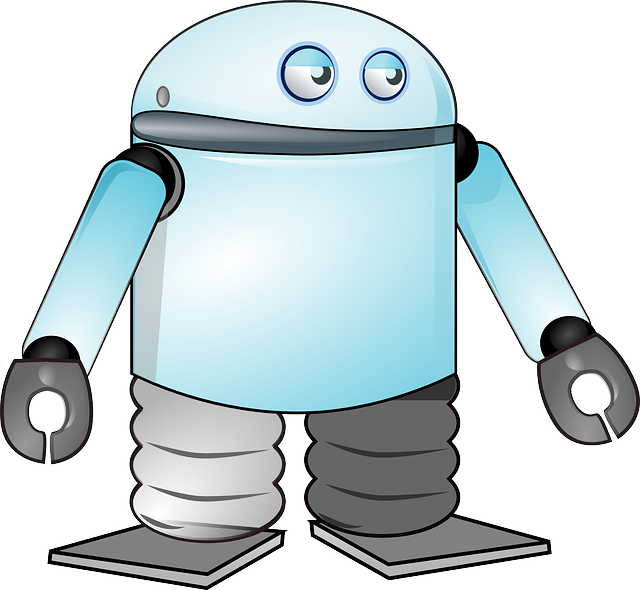閉店したラーメン店の店主が明かした原価率
儲かっている飲食店に関して先日記事を書きましたが、
一方でラーメン店の閉店に追い込まれた店主のインタビューも紹介します。
閉店した『ラーメン無双』元店主の西村政司さんによると、メニューの原価率は次のようになっていました。
メンマは8円(原価率8%)、海苔4枚が13円(13%)、玉子18円(18%)、チャーシュー20円(20%)、
もやし100gが9円(9%)、ネギ50gが20円(20%)、コーン50gが20円(20%)。
「もやしの注文は嬉しかった。安い野菜でボリュームを増やせたからです」。
麺の原価は1玉45円、豚骨ラーメン用の特注麺で52円。
透き通った清湯スープ(しょうゆ・塩・味噌などのタレを入れる前の段階のもの)で約70円、
豚骨スープになると210円~220円となりました。
西村さんは、原価の高い豚骨スープにこだわったことが、閉店に追い込まれた原因の一つと語ります。
「原価率が大体40%以上になったので、利益率はどんどん下がっていきました。
集客数が上がれば利益としてなるんですが、集客率が変わらない状態でこの原価では、持続が難しくなっていきました」と西村さん。
ラーメン業界は厳しく、“10年続く店は10%、20年続く店は3%”の原価率と言われています。
ラーメン店の原価率は、他の飲食店同様に30%以内が健全とされていますが、
このラーメン店は豚骨にこだわり、原価率が40%を超えてしまいました。
具材をこれ以上減らすことはできず、750円のラーメンのスープの原価は140円以内に抑える必要がありましたが、
スープだけで原価の30%になっていたため、具材なしで販売するしかない状態でした。
この結果、
トッピングで利益を確保しようとするビジネスモデルが形成されましたが、
全ての客がトッピングを注文するわけではないため、このような”おまけ”の要素を主な利益源とするのは大きなリスクを伴います。
トッピングの原価率は最高で20%となります。そのため、特にメンマやもやしは、利益に大きく貢献します。
しかし、飲食店の運営は、「料理を作るのが好き」「食べるのが好き」だけでは成功しません。
10年以上継続できる飲食店はごく一部であり、しっかりとした原価計算(人件費含む)、立地選び、マーケティング戦略などが重要となります。
開業には数百万から1千万円の初期費用が必要となり、
その返済に加えて、材料費、人件費、光熱費などの固定費が発生します。
新規顧客の獲得とリピート客の確保、販売価格戦略(顧客に受け入れられるメニューの開発)とマーケティング能力が必要となります。
多くの課題を抱える飲食店のコンサルティングは、広告代理店などにとって大きなビジネスチャンスとなります。
最近では、新型コロナウイルスの影響でテイクアウトやデリバリーの需要が高まるなど、業界環境も大きく変わってきています。
これらの新たな需要に対応するためにも、メニュー開発や価格設定はもちろん、
新しい販売チャネルの開拓や、デジタルマーケティングの活用など、多角的な視点からの戦略構築が求められています。