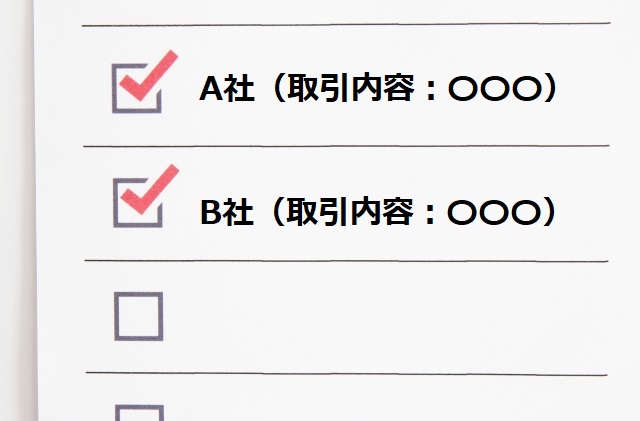4Pと4Cの違いを理解しよう。
企業の商品企画やマーケティングの戦略を考える時に必ず登場するのが『4P』と『4C』です。
『4P理論』は、古くからある伝統的な考え方ですので、
広告業界に限らず多くの社会人の方は知っている方が多いと思います。
一方で『4C理論』は比較的新しい考え方です。
では、『4P理論』と『4C理論』は何が違うのでしょうか?
詳しく説明してみましょう!
『4P理論』は企業側の目線・『4C理論』は顧客側の目線
簡単に言うと、
- 売り手側の目線で考えるマーケティング戦略が『4P理論』
- 顧客側の目線で考えるのが『4C理論』となります。
『4P理論』は50年以上前に提唱された定義で、『4C理論』は提唱されてから30年経過していません。
あとから提唱された『4C』の方が時代にマッチした考え方なのではないか?ということは想像できますね。
大事なことは、どういう経緯で2つの考え方があるのか?
なぜ、『4C』という理論が登場してきたのか?を理解することです。
4P理論とは!
1961年に米国のマーケティング学者(エドモンド・ジェームス・マッカーシー)によって提唱された概念です。
- 製品(Product)
- 価格(Price)
- 流通(Place)
- プロモーション(Promotion)
の4つを定義することでマーケティングを構築します。
つまり、
売り手(企業など)側の視点で『何を、いくらで、どこで、どうやって売るか?』を考えるマーケティング手法です。
4P理論の例
4P理論は、売り手側の都合で物事が進んでいきます。
ちょっと乱暴な言い方をしますと!「自社の技術を活用して、こんな素晴らしい商品を開発したぞ!すごいだろ!」という考え方です。
この考え方には、顧客(購入側)の都合は含まれていません。
モノを開発し、マスメディアを活用して販売すれば、投下する広告料に比例して、“バンバン”モノが売れていく時代の考え方です。
自動車メーカーを例に考えてみましょう!
うちの会社の自慢といえば【四駆】だな。
工場も増設して準備万端。上からも四駆を売れ!と指示が出ているな。
四駆は、かっこいいイメージだから若者に売れるはずだ!そうだ若者に売ろう!
ということは、スポーツタイプにしてカラーバリエーションを豊富にすれば、若者は飛びつくはずだ。
テレビCMでカラーバリエーションの豊富さをガンガンアピールして、販社でチラシを配布して、店舗に来店させれば売れるだろう!
来店者には抽選でディズニーランドのチケットプレゼントでもつければ完璧だな!
ちょっと、極端ですがこんな考え方です。売り手側の都合や思い込みが優先された考え方です。
4C理論とは!
4P理論と同じく、米国のノースカロライナ大学のロバート・ローターボーンによって提唱された概念です。
マーケテイングの多くは米国によって提唱されてきました。
- 顧客価値(Customer)
- 顧客コスト(Customer cost)
- 利便性(Conviniense)
- コミュニケーション(Communication)の4つを定義することでマーケティングを構築します。
つまり、
顧客側(生活者)の視点で、『その商品やサービスは必要なのか?本当に欲しいのか?払う価値があるのか?
簡単に購入できるのか?そして購入して納得できるのか?』考えていくマーケティング手法です。
4C理論が登場した理由は、生活者が豊かになったことで、物理的な欲求が減少。
売り手側の論理だけでは売れなくなった為に考えられた理論です。
4P理論を元に、それぞれの概念を新しい概念として提唱したと言えるでしょう。
下記のように対比していると想定できます。
- 製品(Product)⇔顧客価値(Customer)
製品は、本当に顧客にとって価値はあるのか? - 価格(Price)⇔顧客コスト(Customer cost)
価格は顧客にとって妥当な金額なのか? - 流通(Place)⇔利便性(Convinience)
流通は顧客にとって便利なのか? - プロモーション(Promotion)⇔コミュニケーション(Communication)
一方的な広告ではなく顧客中心のコミュニケーションになっているか?
上記の自動車会社の例でいえば、
- 四駆は自社で開発した自慢の技術だけど、本当に今の時代に求められているのか?
四駆という技術に生活者は価値を感じているのか? - 四駆にしてコストがアップすることが、顧客に受け入れられるのだろうか?
- どんな場面なら売れるのだろうか?今まで通り販社を中心とした接点でいいのだろうか?
- 車の広告はイメージ広告だから、テレビCMでいいと思い込んでいないだろうか?
「車を持つことの価値」という観点から、インターネットや雑誌などでしっかりと分かっていただくことが重要ではないだろうか?
というように、顧客の立場になってマーケティングを構築していくのが『4C理論』です。
まとめ
『4C理論』が注目されるようになった大きな理由は2点あると思っています。
第一の理由は、高度成長の時代が終わり、各家庭にモノが揃い、モノ余りの時代になったことで、企業側のメッセージで簡単に生活者は動かなくなったことです。
そして、時を同じくしてインターネットが普及します。インターネットにより生活者は自由に情報を取得できるようにもなります。
このような理由により、売り手側は顧客目線で、顧客が本当に必要にしているものは何なのか?を考えなければ通用しなくなりました。
広告の世界でいえば、『AIDMA(アイドマ)の法則』から『AISAS(アイサス)の法則』への変化。
『メディアミックス』から『クロスメディア』へと考え方が変化したのと同じ流れです。
SNSが普及し、顧客が自由に情報を発信できるようになった時代においては、顧客中心の考え方は今後もより重要視されていくことは間違いありません。
『4C理論』を中心に『顧客目線で考える』ことは忘れないようにしましょう!
『トリプルメディア』の考え方も覚えておきましょう!